AIで普通の動画を3D動画に変換する
〜一の月、シンビジウム〜
カトレアで過ごす最後の一月。
普段は王宮に居ない皇太后も、
息子との最後の一時を過ごすために王宮にやってきた。
静かなカトレア王宮が珍しく賑やかになった。
「アーウィング、チェスの相手をしようか?
それとも、楽士を呼んで演奏会を開こうか?」
「国王陛下、またこちらに来られて…困ります!
貴方がこちらにいらっしゃっては政務が滞ってしまいます。
至急、お戻り下さい!」
秘書官のバロータが眉間に皺を寄せながら詰め寄る。
アスファルドはアーウィングに負ぶさるようにしてぎゅっと掴まえて放さない。
「多少、政務が遅れても構わん!
兄弟で過ごす時間はあと僅かなんだぞ。
ただでさえ余り会えなかったのだ。
何と言われようと私はアーウィングと過ごす!」
「…陛、下…!」
バロータの頭の神経がプツリと切れたような気がして、
アーウィングはおそるおそる助け舟を出した。
「僕…兄上の仕事ぶりを拝見したいな。
これから僕も国を治めるにあたっての参考にしたいのです。
ダメでしょうか?」
見上げるようにして背後のアスファルドに尋ねる。
「そうか?よし、じゃあアーウィングにも少し手伝ってもらおうかな?」
「はい、よろこんで」
バロータはホッとした。
すると、背後でシクシクと泣き声が聞こえた。
「なっ…皇太后様!」
「せっかく一緒にお庭を散歩しようと思いましたのに…」
「母上…あとでお付き合いします。
これから兄上に政務について学ばせていただく所ですので…」
すると、恨みがましい表情でじっとアスファルドを見て、
「わかりました。
私はクリビアとアルシードとお散歩しますから、ごゆっくり…」
と言い、侍女たちを引き連れて行ってしまった。
「すみません。子供っぽい母親で…」
「あの方はいつも私に意地悪なんだよ。
君を取り上げた事を今でもずっと恨んでいるんだ。
当然だよ。可愛い盛りの子供と引き離されたんだ」
父王が亡くなった後、その思い出の多い王宮は辛いからと
モナルダ妃は幼いアーウィングを連れて離宮にその居を移した。
それから暫くして嗣子の居ないアスファルドの後継者として
アーウィングは皇太子の地位に就き、母子は引き離された。
その事をいつまでも申し訳なく思っているアスファルドには、
モナルダの子供っぽい性格が理解できていなかった。
「そして、また私はお前を他国に行かせるんだ…」
アスファルドは家族の絆というものを一番に思う。
その情に厚い性格が政務に響かないのは
国王としての責任感と能力の高さによるものだろう。
実際、即位してからの評判は高く、
アーウィングはそんな兄を心から尊敬していた。
「僕は、幸せになる為にクレツェントに行くんです。
兄上には感謝しています。
きっと、幸せになります」
じっと相手の目を見つめるのはアーウィングのクセだ。
アスファルドは幼い頃と変わらないその瞳の輝きを愛しく思う。
永遠に変わらないものなんてありはしないけど、
君のその眼差しを信じていたい。
輝き、見失わないように真っ直ぐに進んでいけば、
いつかの未来は傍にある。
だから、君はそのままで…
カトレアで過ごす最後の誕生日、
アーウィングの元にはクレツェントにいるリディアから贈り物が届いた。
「これは…シンビジウムだね」
『貴方の気取りのない心に私は感謝しています』
そう呟く声が聞こえたような気がして、アーウィングは嬉しくなる。
「おめでとう、アーウィング王子」
「セラトリーク殿…」
優しげな微笑みをたたえた青年貴族、それは年上の甥だった。
彼はリディアの姉姫であるライラと婚約していた。
だが、未来の花嫁は魔族によって奪われてしまった。
それが原因で今や彼は魔族討伐に積極的な人物になってしまった。
争いごとを好まず、穏やかで優しかった彼を変えたのは
叶えられなかった恋の傷である。
それを知っているアーウィングは、リディアとの婚約の話が持ち上がった時、
それを彼に譲ろうとしていた。
だから、今でも彼に対して申し訳なく思う気持ちがあった。
「ありがとう…」
「リディア王女からの贈り物…素敵だね」
「うん。彼女は彼女なりに僕や僕の国を理解しようと努力してくれてる…
素直に嬉しいと思う…」
正直に気持ちを話した。
「王子はいつも僕に対して申し訳なさそうにしてる…気にしなくて良いんだよ?」
「えっ…?」
「僕、これでも貴方より大人なんだから、大丈夫なんだよ?
確かに、貴方は"叔父さん"にあたるけど…貴方が思ってるほど僕は弱くないよ」
サラリと赤みのある茶色の髪がなびく。
幾分、繊細な造りだが、その横顔はどこか兄のアスファルドと似ている。
「セラトリーク殿は、本当にリディア姫と僕が結婚する事を認めてくれるの?」
「もちろん…。それにね、彼女じゃダメなんだ。
僕の心はライラ姫にあるから」
切なげに瞳を細めるセラトリークの表情から、
今も彼がライラに焦がれている事を読み取った。
「リディア姫は、確かに美しく、ライラ姫の身代わりにできただろう…
でもね、代わりにはできるけど、代わりにはなれないんだ。
ライラ姫はもう、どこにも居ないから…」
「そう。それを聞いて安心した」
「……?もし、僕が認めないと言ったらどうしたの?」
アーウィングは困ったようなカオをした。
「もう後戻りはできない、譲る気はない!ってハッキリ言おうと思ってた…」
「ははっ…成る程、正解だ!
貴方を相手に選んだヴィクトル王は正解ですよ。
貴方なら、きっと姫を幸せにできる!」
「そう?そうかな…?」
「ええ。貴方は…貴方だけは彼女ただ一人を見つめ、必要としている。
それは、幸せの条件だと思います。
誰もが自分がたった一人の人になれることを望んでいる。
貴方にとっては、彼女がそうなのでしょう?
あとは、彼女にとって貴方がそうなれば条件は満たされる。
その日は来る、と僕は思いますよ…」
アーウィングは複雑だった。
彼女が望むたった一人の人が誰なのか――自分は知ってしまっている。
彼に自分は勝てるだろうか?
「難しいけど、頑張るよ。諦める訳には行かないし、先は長いしね」
精一杯の笑顔で返す。
セラトリークはその笑顔を見て、懐かしいと感じた。
アーウィングは彼が焦がれた少女と同じ輝きを持っている。
まっすぐで、周りを照らすように温かい心の持ち主だ。
彼に愛されて嬉しくない人物が居たら会ってみたいくらいだ。
(だから…貴方が幸せでありますように…)
クレツェント王宮のリディアの部屋にも、シンビジウムが咲いていた。
「今頃、この花は届いているかしら?」
それはリディアからアーウィングへのメッセージだった。
「本当に、感謝しているのよ。貴方に…」
シンビジウム、その花のように色付く淡い気持ち。
気取らないその心に惹かれて、ここに辿り着いた。
水面に浮かぶ小舟のように
揺れる私を貴方へと導いて…
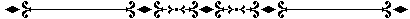
セラトリークが登場!彼はライラの元・婚約者。
彼はアーちゃんと違って実務的な仕事とかしてきてない典型的な貴族です。
むしろ音楽家くらい言ってしまって良いかも。
だから、ライラが女王になっていたら、意外と上手く行ってたんじゃないかな?
政務を負担するわけじゃなく、夫として彼女の安らぎになれたと思うんですよ。
でもって、アスファルド兄上〜!LOVE!
弟を溺愛している年の離れた兄って設定、大好きなんです!
もしくは息子に本気で張り合おうとする若作りの父親とか。
前者がアスファルドなら後者はモナルダ(彼女の場合、母ですが…)。
アスファルドはモナルダを好きという時期があったので、
彼女の子供っぽい性格からくる意地悪を、イチイチ真に受けて、
その結果、落ち込んでしまうんですね。
そんなアスファルド兄上が僕は大好きです。
深愛〜花は囁く〜・7に続く。